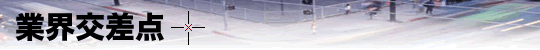この人に聞きたい:第178回
(週刊水産タイムス:09/02/09号)
築地トップインタビュー
中央魚類社長 伊藤裕康氏
今期の第3コーナーも過ぎ、大勢がほぼ見えてきた。前半戦は「買い負け」、後半は「買い勝ち」と、めまぐるしい1年となったが、こうした中で築地の荷受各社はいかに対応したか。新年度への抱負も含めて、各社トップにインタビューした。
――第3四半期の業績を公表したが。
伊藤 非常に厳しいと受け止めている。在庫増もあるが、総体的な消費不振が根源にある。今期もあと2カ月。ここまできたら悪いものは悪いとして、包み隠さず出すべきものを出し、すっきりした形で次を目指そうと思う。
――100年に一度の経済危機と言われている。しかも水産業界は生産者も流通も小売も、全てにおいて儲かる人がいない。
伊藤 水産業界を取り巻く今の厳しい環境を一過性と捉えていては、永遠に解決できないだろう。全体的な構造不況の中で、荷受として何が必要か、何ができるのか、また何をしなくてはいけないかを、この際、徹底的に洗い直してみたい。もはや生半可な対応では済まない。少々の覚悟では乗り切れない。
――産地と量販店の直接取引が一部で始まったが。
伊藤 マスコミにとっては、いいネタでしょうが、あれが将来の水産物流通において本流になるとは到底思えない。直接取引の全てをダメというつもりはないが、直接取引が本当に円滑な流通と漁業者のためになるのか。市場には市場なりの役割と機能があり、中間流通を抜けば全てが解決するような単純な話ではないはずだ。
――漁業者も、市場も変わる必要がある。
伊藤 総合的で合理的な水産物流通のあり方を考える時期にきている。漁業者と量販店との直接取引でマスコミが言うような「新しい流通の波」ができたとは思えない。
――行政も後押ししているようだが。
伊藤 漁業者には様々な補助金があり、昨年の燃油対策費もそう。経済的な支援は一種のカンフル剤にはなるだろうが、それが長期的な体質改善にはつながるわけではない。漁業もあくまで輝ける産業を目指していくべき。市場の役割というものも当然存在する。この問題は全漁連とも話し合っていく。
――生産者、市場ともに今後のあり方を探っていく上でヒントにはなる。
伊藤 主流ではないにしろ、そこから何かを学べるヒントにはなるかもしれない。「実態」から学んでいくという姿勢が大切。漁業者も単に獲ってくればいいというわけではなく、売ることも考えながら獲らなければならない。そこに我々とどういう連携ができるのか、模索する必要が出てくる。獲る方の理屈、市場の理屈を互いにぶつけ合っていてはたどり着けない結論だろう。
――新年度もさらに厳しくなりそうだ。
伊藤 今までの概念や成功事例を踏襲すれば何とかなるという時代ではない。集荷や品揃えなど、求められる市場の公共的なベースを守りつつ、伸ばすべきもの、削るべきものをきちっと分けて考えていく。