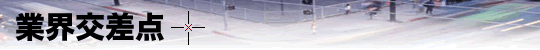冷凍食品(冷食)・冷凍野菜・お弁当の売上・取扱ランキング・ニュース
|
|
|
|
|
|
 |
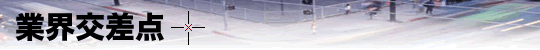 |
この人に聞きたい:第1016回
(週刊冷食タイムス:26/02/03号)
「基盤をがらりと変える」
旭食品 代表取締役社長 竹内 孝久氏
三角形のサプライチェーンへ
フードランド初日の朝礼で、竹内孝久社長は寒い中でブースを設営する出展メーカー担当者をねぎらうとともに、「食品流通業界を盛り上げよう」と、次のように出展メーカーに呼び掛けた。
展示会開催に当たり、食品流通業界をどのように盛り上げていくべきかを考えている。食品流通業界は小売ベースで50兆円、中間流通を含めると96兆円の大きなマーケット。戦後の復興期にそれまでとは異なる食品流通が生まれ、80年間脈々と多くの先輩の方々の”想い”やこだわりをつないできた。
日本の食品流通システムは海外からは「複雑で効率が悪い」と見られる一方、「スピードや納品率の精度が高く品質が良い」とも認識されている。「非効率に見えるけどとてもいい」。それが80年で日本が築き上げた世界に冠たる食品流通システムだと思っている。
しかし、そのサプライチェーンが少子高齢化や労働力の減少で曲がり角を迎えている。この転換期をどのように旭食品グループは乗り越えていくべきなのか? 今のサプライチェーンをただシュリンクさせるだけのか?
あるいはDX化だけで乗り切るのか? それだけでは恐らく先細りになるだろう。
私はDXも含め社会基盤をがらりと変えることによって乗り切っていくことが大事だと考えている。
サプライチェーンの入り口から出口を結ぶだけなら直線だが、その線の上に点を置いて結べば三角形になる。この面積を大きくすることが大切であり、そのような構造のサプライチェーンへの転換が必要となる。
三角形の頂点を高めるためのキーワードの一つは”専門性”。
旭食品は専門知識を持つ「特選隊」チームを作り味噌や茶を提案営業しており、こうした”人間力”や現場力を高めることで専門性を追求してきたが、これをもっと進めていく必要がある。
当社は魚介や菓子等いろいろなグループ企業を有し、その数も増えている。新しい市場をどんどん取りに行くことによって価値を高めている。これが二つ目。
三つ目は伝統。高知が世界に誇る祭りと言えばよさこい祭り。このよさこい祭りと”食”を掛け算することで新しい市場を創ることができると。今回の展示会でも、よさこいとの掛け合わせでいろいろなお客様を活性化する”お役立ち”を提案する。メーカーの皆さんもよさこいブースに立ち寄っていただき、得意先と一緒になって売場を盛り上げてほしい。そういう仕掛けにも今年は力を入れていきたい。
最後はAI・デジタル化。これも今回の展示会で「AI孝久社長」という形で紹介しているが、AI・デジタル化は始まったばかり。しかし、食品流通を今後大きく変えていくだろうということは皆さん気づいているかと思う。
当グループもAI・デジタル化でまだまだ可能性を広げていけるし、新しい食品流通システムを作っていきたいと考えている。皆様のご協力をよろしくお願いする。
|
|
 |
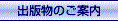 

\ 15,400(税込み) |

\ 4,400(税込み)
|

\ 2,750(税込み)
|
 |
\ 2,640(税込み)
|
|
|
|
|