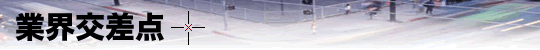この人に聞きたい:第348回
(週刊水産タイムス:12/07/09号)
活鰻消費が半減
日本鰻輸入組合 理事長 森山 喬司氏
日本鰻輸入組合の森山喬司理事長に輸入ウナギを中心とした今夏の需給動向と秋以降の展開などについて聞いた。
深刻なのは、ウナギが売れる時期なのに売れないこと。今回の活鰻相場の高騰で、蒲焼き専門店ではメニュー価格の値上げを実施。それに伴い活鰻の消費量が半分近くまで落ちた。
蒲焼き専門店での消費が減った上に、加工場向けとなる国産活鰻も加工が進まずに行き場を失い、一時的に供給過剰な状態となり相場が下がっている。
4月下旬に1kgあたり国産で5000円、中国産で6000円だった池上げ価格(ヒネ物)は、6月下旬時点で九州3750円、三河4200円、中国産・台湾産4200〜4400円まで急落した。
中国産活鰻はもう一段相場が下がらなければ出番がない。ただし、中国は国内消費があるのであわてていない。4000円前後で下げ止まるのではないか。
活鰻の相場は国内の加工場が稼働を始める秋まで下がり、ある程度まで加工が進んだ段階で上がり始めると見ている。今年は230万円/kg前後の高いシラスが入っているので、5000円前後までは上がるのではないか。
中国産蒲焼きも6000〜7000円/kgと相当高いものになる。新規の買い付けの話は、夏の販売動向を見てからになる。
業界の話題といえば、国内の一部の養鰻業者も異種ウナギの養殖を始めた。中国と台湾でも異種ウナギの養殖技術について研究を進めている。加工品として異種ウナギが市場に流通する可能性は十分にある。
活鰻でいえば、異種ウナギ以外に韓国産(ジャポニカ種)が挙げられる。価格高騰で韓国での消費が減り、対日輸出をめざしている。6月に視察に行き、品質管理や出荷体制を確認してきた。
昨年12月に活鰻が命令検査になるなど、中国や台湾に比べて品質管理体制はまだ整っていないが、今後期待したい。