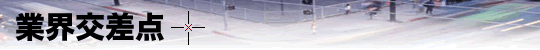この人に聞きたい:第992回
(週刊冷食タイムス:25/07/29号)
新分野の開拓に常に挑戦
野口食品 野口 昌孝社長
(のぐち・まさよし)大卒後、加ト吉で2年間勤務後、父・治郎氏が経営する野口食品に入社。父の急逝に伴い2001年3月現職就任。父の名を冠した学校「ジロー学校」をカンボジアに02年寄贈(現在までに計4校寄贈)。20年藍綬褒章受章。関東給食会元理事長、アイエフエー前代表取締役、日給連第9代会長・現名誉会長。1957年6月横浜市生まれ、68歳。

粗利重視、顧客の偏りなく
2027年、創業100年を迎える野口食品。創業者・舜治氏、2代目・治郎氏、現社長の昌孝氏へと受け継がれたのは粗利重視と「新分野への挑戦」の精神。食料品店としての草創期から事業所、学校給食、仕出し弁当はじめ他分野への販路拡張、冷凍食品の先駆的導入等について聞いた。
――創業100年を2027年に迎える。事業継続の秘訣は何か。
野口 創業者で祖父の舜治、2代目で父の治郎の代からこれまで、常に心がけていることを改めて考えてみると、新分野の開拓に常に挑戦していることかもしれません。新しいことに取り組まなければ、企業の寿命は30年と言います。
1927年(昭和2年)創業から現在に至るまで太平洋戦争や大震災、バブル崩壊、パンデミックなどがありながらも事業を継続して来れた根底には、粗利を重視しつつ、常に新しい分野に挑戦し続けたことがあると思います。
当社の前身はパパママストアの食料品店で、横浜市鶴見区下末吉で創業しました。やがて京浜工業地帯の工場給食向けの食材納入を始め、事業所給食、学校給食、仕出し弁当向けが3本柱の業務用食品卸が本業となり、さらに、ほかほか弁当、外食、市場、コンビニベンダーなどに売り先を広げ、顧客の偏りをなくし現在に至っています。
――小売店の野口食料品店が戦後、株式会社へ改組し業務用食品卸の野口食品となった。ホームページで公開している沿革を見ると、1958年(昭和33年)に「冷凍食品を業界に先駆けて取り扱い開始」とある。この経緯は。
野口 1958年といえば、29年生まれである父・治郎は30歳前と若く、新しい商品分野である冷凍食品の導入に意欲満々だったはず。当時、後発で小規模の業務用食品卸に過ぎなかった当社が缶詰や調味料等の一般常温食品で商売をしようにも限界がありました。先発で大規模の食品卸の2次店、3次店に位置付けられ、1次店に利益を吸い上げられるため利益が薄いものになってしまうからです。そこで既成の特約店制度に染まっていない冷凍食品メーカーとの取り組みに治郎は積極的になったのでしょう。当社に冷凍食品を売り込んできたのは日本冷蔵(ニチレイ)販社の営業マンだった田井扶娑夫氏だったと聞きました。
――昭和41年(1966年)協同組合関東給食会を発起人として設立と沿革にある。
野口 関東給食会の前身はニチレイ業務用特約店会ともいえる日冷スター会で、やがて任意団体の関東給食会となり、1966年に協同組合として発足しました。田井氏はニチレイを辞めて関東給食会専属となり、治郎は発起人として参画しました。治郎が当社の社長に就いたのはその翌年の67年です。
学校給食の販路開拓に注力し、川崎市学校給食会、東京都大田区教育委員会中学校、横浜市学校給食会の指定業者となり、業務用食品卸としての事業基盤を確立しました。治郎は学校給食物資開発流通研究協会(74年)、全国給食事業協同組合連合会(78年)、日本外食品流通協会(79年)の設立にも発起人として深く関わりました。
97年には大京食品、ウルノ商事、コーゲツらのオーナーと国際食品流通同友会(アイエフエー)を設立しました。
当社の年商は80年当時31億円、鶴見区大黒町の現本社・流通センターを新設した91年当時は約65億円と、販路の広がりに伴い事業の規模が拡大しました。ところが現本社が完成した頃にバブル経済が崩壊し日本経済が低迷し始めました。それでも当社は新設した流通センターを武器に、治郎の代に年商100億円の目前まで行きました。
連結売上高200億円に/さらに上めざして設備投資
――現況は。
野口 前8月期業績は単体売上高130億円、ヴェスティ・フーズ・ジャパンなど関連会社の売上げを含む連結売上高は200億円となりました。
今期売上高は単体142億円を目標に掲げ、ほぼ達成の見込みです。新規顧客の獲得が増収要因となりました。
創業99年目に当たる来期は単体売上高150億円超えを計画します。販路、業態ごとの徹底売込み、成長分野や利益率の高い分野、利益率の高い商品、スケールメリットが出る商品の売込みなどを続け、将来的に単体200億円、グループ300億円へのステップアップをめざします。そのために設備投資も検討します。
現在の販売拠点(デポ)は横浜本社のほか、湘南営業所、千葉営業所、相模原営業所がありますが、営業拠点をさらに増やすことを検討しています。売上げ拡大に伴い91年竣工の本社・流通センターは手狭になってきました。入庫の合理化で手狭解消を図りつつ、新たなデポが出来れば本社の在庫を分散化でき、手狭の解消につながります。
――業界内外に訴えたい問題は。
野口 壊れて使い物にならなくなったパレット(雑パレ)を納入業者が引き取らないため、雑パレを当社が仕方なく引き取り、粗大ごみとして出さざるをえません。雑パレを捨てるにも、4t車積載当たり12万円の支出になります。雑パレは問題だと思います。